全体を通しては、もうすぐ停年の誕生日を迎える私が今後の生活に対する不安を抱えて、第二?の就職口を探しながら日々を送っています。しかし思うようにはならず、焦りや睡眠不足と食欲の減退、思考の混乱を感じています。そんな苦しさに喘ぐさなかに嫁に出した娘が重病を煩い今夜危篤となります。持って行きようのない困難に打ちひしがれ自死を選択してしまいます。主人公人生最後の或る二日間の物語です。
1.主人公佐伯と語り手の人称
この作品では佐伯本人はほぼ何も語っていません。佐伯という三人称で語り手である作者の永井が口を開きます。ただ何カ所かは表現の異なるところがあります。順にみてみましょう。
①退社後に再就職依頼に出かけた先で、不在で会えなかった場面。
―――彼も主人に面会できると思って出かけたのではなかった。・・・―――
という箇所では佐伯が三人称で自分を表現しています。
②柱時計の振り子を止めるかどうか迷っているところ
―――ゼンマイを巻く鍵と一しょに、そこに入っている物を知っていた。それは彼が、そこへ隠した・・・―――
この箇所は語り手(作者永井)の言葉でしょう。
③柱時計が死んでしまった後、未来の想像として
―――その翌日の夕刊を、もし佐伯に見せることができたら、・・・―――
ここは、語り手永井の言葉であると同時に佐伯本人でもあると思われます。
④翌日の夕刊紙面を想像しながら
―――これは、あなただけにお話しますが、僕がいよいよ死ぬという時まで・・・―――
この語り手は佐伯本人が自分に向けたものであろうと思います。
このように人称に変化をつけながら、主人公の佐伯には発言をさせずにそれでいて主人公が胸中を吐露しているかのような表現とすることで、読者を作品に引き込む構成になっていると思います。
2.柱時計と私の人生
A章冒頭に柱時計の振り子の音が佐伯の眠りを妨げたことを述べています。後の展開でこの柱時計の振り子の音は彼の人生と密接に絡んできます。出だしの文章で作品全体について読者に何かしらを暗示します。
①振り子の音で安眠を妨げられたのに、乗っている電車の騒音は気になりません。
―――「柱時計の振り子の音で、けさ四時まで、完全に眠れなかったんだからな」
佐伯は自分に言い聞かせた。そのくせ、自分を乗せて走っている電車の騒音には無感覚だった。・・・―――
この柱時計は二十数年前に結婚祝いにもらったもので、もうすぐ55歳の停年を迎える昨夜から急に自己主張を始めます。結婚後格別な問題もなく、少なくとも一人の子供にも恵まれ、懸命に仕事をしてきた佐伯はその生活の充実感から、夫婦や子供を見守り続けて時を刻んできた振り子の、カチコチという音さえも気づく事はありませんでした。それが、昨夜から急に振り子の音が耳につき始めます。夫婦になり子供ができ、その子供が嫁いでいったその全ての時間を柱時計の私が支えてきたのだぞと言わんばかりに聞こえます。通勤に利用する列車の大きな騒音は、これまでは出社後の段取りや予てからの懸案事項、会議の準備など等で頭の中は一杯でした。列車の騒音なんて耳に入ってきません。周囲の状況も格別目に入るわけでも無く、見れども見えず聞けども聞こえずでした。佐伯は会社ではそれなりの立場にあったのでは無いかと思われます。
②懸命に仕事をする佐伯は自分の立場からしか物事を見てこなかったが、今は違う観点から物事をみるように
なってきます。
―――向こうから見れば。こちらの車両も同じように揺れているのだなぞということを、佐伯は考えは
しなかった。・・・―――
乗っている列車の後ろの車両が揺れているのを見ても、後ろの車両から前を見るという観点が働かない。それほどひたすら前を向いて働き続けてきたらしい。それが停年まで二ヶ月後の秋に迫った今、自分の頭の中からは現在の仕事のことはすっかり陰を潜めてしまいます。
3.現実と妄想:エンゼルとサラリーマンと孫
A章後半とB章では赤ん坊と自分を重ねながら妄想の中で会話をします。
①生後四〜五ヶ月の子供を抱いた若い父親が列車に同乗しています。夜10時近くの時間帯に高く抱かれた赤ん坊はしきりに列車の吊り手を捕まえようとしています。
―――何度目かに、大きく抱き直される瞬間だった。両手を挙げたまま、嬰児が宙に飛 ぶように見えた。大きな瞳 が、何らの不安なく、大胆に白い吊り手を見つめていた。「ああ、天使のようだ」と、その時佐伯は連想した。・・・―――
自分が何故誕生日で時の流れを断ち切られてしまうのか納得できない。偶々見かけた父親に抱かれた乳児が、しきりに吊り手を掴もうとしている光景とこれまでの自分が吊り手にぶら下がって通勤する光景が重なる。しかし白いおくるみにくるまれた乳児が、一瞬天使に見えた時、サラリーマンの自分とエンゼル (遭遇した幼子) のどこが違うのかという感覚に襲われる。これまでの価値観が全て崩れ去り、自分が生きてきた道を見失います。列車内の会話は全て佐伯の妄想です。現実と妄想の区別が付かなくなってきてしまった笑えない切なさと自問自答が展開されます。
4.時を止める=時を駆ける
C章では、疲れ果てて職探しの徒労な一日を終えての夜に展開します。この章での夢から目覚める展開は名文だと思います。そのままのとは言いませんが、何かしら似たような経験を作者が持っていたのか?とさえ感じます。先ず居るはずのない妻の足音に続き、柱時計が振り子の動きに合わせてつぶやき始めます。
―――「この家は、つぶれる、かも、知れません。しかし、つぶれる、までは、私が、 こうして、支えて、います、
この家は」―――
その後、次第に目覚めて娘の危篤を知らせる電報を受取ります。二ヶ月後の秋に迫った自分の停年と娘サダコの危篤。それと書かれてはいませんが、感想文を書いている私は、娘が死産した子供 (=エンゼル) への悲しみが同時に迫って来たのではないかと思います。
「サダコキトクスグコイ」 の電報を読んだ佐伯は、妙案を思いつきます。
―――「そうだ。あの振り子を止めればいいのだ」―――
柱時計の中に隠してあった睡眠薬の箱を取り出すと同時に振り子を止めました。明日の夕刊見出しを想像しながら、「濁りのない気持ちで懸命に前を向いて歩き続けることでは、サラリーマンもエンゼルも同じじゃないか」 と考えます。 時を止めれば孫の死も娘の死も自分の停年も、全てがリセットされ無かった事になる。そう考えるしか手立てが無くなった或る一人の月給取りの悲哀を、読み苦しくない文章で感じることができます。
5.「一個」の指すもの
一個という題名の真意は掴み兼ねていますが、真面目に努力を重ねて生きてきた自分も、停年という日をもって定期券の期限切れのように扱われる。人づてに職を求めても皆にべもなくあしらわれる。嫁いだ娘は危篤、孫もいない。現実としてあるのは迷い悩みもがく自分だけ。その苦しさを分かってくれる人は誰もいない。唯一人の自分です。
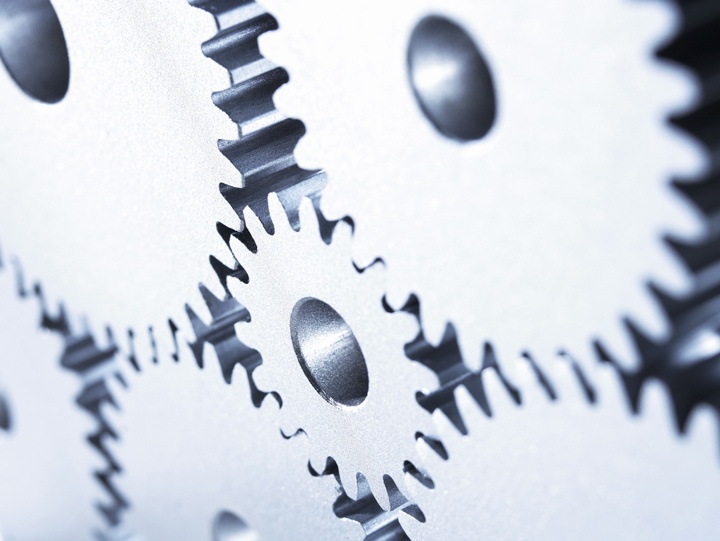
フリー素材
前の頁、浮世の画家 次の頁、あらしのよるに VolⅢ.目次へ VolⅢ.トップ頁
Vol.Ⅱ トップ頁 Vol.Ⅰ トップ頁